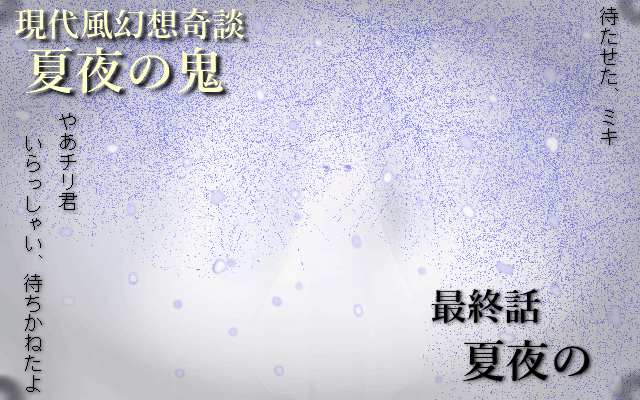夏夜の -0-
*K.M*
母の愛は私のものだった。
母性に包まれ、慈愛に育まれ。私を形作るありとあらゆる要素はすべて、母から受け継がれたものだと言っても過言ではないだろう。
人を生み出した存在が神であるというのなら。
私にとっての神とは、即ち母のことで間違いなかった。
それが掛け替えのない存在であることはすぐに理解できたし、いつかは別れが訪れるのだという事実さえ空想に思えた。
母体より分かたれてなお、私は母の一部だった。そう考えれば、己の四肢も頭も顔も、五臓六腑に至るまで愛おしかった。
私とは、母の愛そのものである。
ある種の崇拝に陥るほど、当時の私は母を慕ってはいたが、しかしそれを諌めたのもまた母であった。
旧家の長男として。
人の上に立つ者として。
父にも祖父にも劣らぬ家長として大成すること。それが使命であると、それこそがこの命の役割なのだと。母は私に言い聞かせ、そして相応の教導を示してくれた。
それはときに父よりも厳しく、また激しいものではあったが。けれどその地盤に母の愛情があることを、私は決して忘れはしなかった。
愛故に。愛故に。
私は幸福であったのだ。
あの母の下へ生まれてきたことを、私は何より誇りに思っていたのだ。
弟が生まれた。
母を奪われた嫉妬に狂うような、そのような愚挙に私が陥らなかったのも、また母のおかげであった。私は弟を家族の一員としていち早く認め、長男として、将来の当主として、守るべき対象であると決意を固めた。
或いはその結果、命を落とすことになろうとも構わない。そのときは全てを弟に引き継げば良かった。一族の存続のためならば、命も地位も、私の胸には何も要らない。
なぜならそれが、母の望んだ私の姿であったからだ。それでいい。構わない。あの母から生まれ落ちた兄弟なれば、私の理想を託すことにためらいなどない。我が身は英霊となりて、永劫、一族を守護する礎となればいい。
愛が。母の与えてくれた愛があれば、それさえあれば私は進める。
それが世界、その全て。
家族との愛が。母との愛が。私の胸に、この心に、繋がっている限り。
私は戦う。
私は生きる。
私は糸を手繰り寄せる。
この命、尽きるまで。
――――
妹が、生まれた。