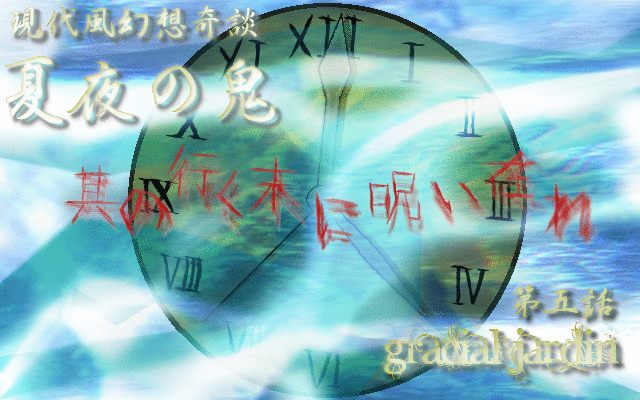Gracial Jardin -0-
溢れ続ける血潮と共に流れ出すように、その体温は瞬く間に失われていった。
腕の中で、虚ろな目をした男が、いよいよその瞼を閉じようとしていた。
その神秘的な碧眼の輝きが、何より愛おしかったのに。
その瞳が最早、何も映してはいないことに、奈落の最果てを俯瞰するほどに絶望した。
なぜ。
一体何故、このようなことになったのだ。
愛しい人とただ二人、平穏に暮らしていられたらそれで良かったのに。
一族の誇り?
信仰の果てに至る理想郷?
なんだそれは。なんなのだ。
そんなもののために、何故我らは朽ち果てなければならないのだ。
血も。空も。全ては、我らを生かすための装置でしかないはずだろうが。
どうして我らが、その道具ごときに殉じなければならないのだ。
許さぬ。
認めぬ。
断じて受け容れぬ。
それが運命だというならば。我は人を捨て、真の悪鬼へと変じよう。汝らが我をそう呼んだように。かくあれかし、かくあれかしと、この身を外道へと投じよう。
満天下に広がれよ、無間の氷原。
白く、白く。
蒼く、彼方へ。
我は大紅蓮を統べる者也。
――時よ、止まれ。